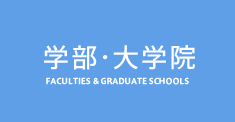Aくんの思い出
井上 光一 (臨床心理学・学生相談)
もうだいぶ前のことが・・・。駅へ向かう帰りのバスに乗っていたときのことである。途中のバス停で小学生ぐらいの女の子が泣いていた。運転手がドアを開けて「乗りますか?」と声をかけると、「○○に行くには、どのバスに乗ったらいいですか?」としゃくりあげている。バスを乗り間違えてここで降りたものの、そのあとどうしたよいか分からず泣いていたようである。女の子が行こうとしていた○○は、駅とは反対方向の、バスの本数も少ない路線にあった。もうだいぶ遅い時間だった。「かわいそうに・・・」乗客たちの同情が女の子に注がれた。運転手は時刻表を調べると、決心したように「駅発○時○分のバスがありますから。乗ってください」と、女の子をバスに乗せた。このまま駅まで送るというのだ。乗客はみな腕時計を見た。「駅発○時○分のバス」に間に合うか微妙な時間だった。女の子を乗せると、バスはすごいスピードで走り出した。乗客は手すり・つり革にしっかりとつかまった。かなり乱暴な運転だった。カーブでは乗客がみな右に左に大きく揺れた。いつもなら続けて赤信号に引っかかるはずのふたつの交差点も、黄色信号のなかノンストップで通過した。幸い途中のバス停で乗ってくる客もなかった。駅まであと二駅というとき、控えめに降車ボタンが押された。『次、とまります』アナウンスが流れた。大きなカーブに差し掛かりながら運転手が「降りられますかー?」とたずねた。乗客たちの目がサラリーマン風の男性の背中に向けられた。一瞬間があって「やっぱり、いいです」。やさしい声だった。バスは横転するのではないかと思うほど大きく傾きながらカーブを曲がりきった。乗客たちは揺れ戻りながらにっこりと顔を見合わせた。無事に駅に着き、女の子が走ってゆくのを見送った。何か良いことをした後のようなすがすがしい気持ちだった。

ところがバスを降りたその直後から私は悲しくなってきた。どうしてだろう。私の少し前に降りたサラリーマン風の男性が、駅とは反対方向に歩いてゆくのを見ながら、その痩せた背中から発せられた「いいです」をぼんやり辿りながら、私は小学生時代に失ったある友達のことを思いだしていた。
Aくんは、近所に住むひとつ年下の幼なじみだった。Aくんは快活で賢くて、控えめだった。何でもよくできるのだが、争うことなくいつも「いいよ」と他の子に譲っていた。私はそんなAくんが好きだった。Aくんも私を慕ってくれていて、よく一緒に遊んだ。やがてお互い同学年の友達と遊ぶことが多くなってからも、学校や公園で、通学路で、Aくんのまなざしが私に向けられているのを感じた。目が合うと何だか照れくさかった。不思議な関係だった。そんなAくんがある時から入院した。親にたずねても「そのうち退院するでしょう」としか教えてもらえなかった。どれぐらい経ったのか、親と一緒に病院に行った。ガラス張りの部屋から点滴をつけたAくんが出てきた。親同士が話をしている間、Aくんと私は面会室でふたりきりだった。Aくんはすっかり痩せて、骨のかたちがはっきり見えるほどだった。頭には毛がなかった。大きな目だけが前と変わらなかった。私は見ていられなかった。Aくんの目から大粒の涙があふれてきた。「こうちゃん・・・」(私はこう呼ばれていた)。「Aくん・・・」。それが最後だった。病院のスタッフが診察の時間だと言いに来た。「もう、いいかしら?」「はい、いいです」。
Aくんの通夜は賑やかだった。自宅に集まって、お酒を飲んでみんなで楽しく送り出すらしい。大きな笑い声が私の家まで聞こえていた。ちょうど世の中の「わからなさ」を感じるようになってきた頃だった。私は落ちつかず、工具箱を持って庭に出ると、犬小屋の「修理」をはじめた。突然の修理に老犬コロが戸惑っていた。何でもよかった。ただ金槌を打ち鳴らしたかったのだ。「こんな夜に何をやっているの?」親から咎められたが、私は続けた。「Aくん、Aくん」と。