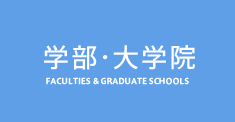再生医療に期待すること
薬理学研究室 角山 圭一 准教授
ここ数年、テレビや新聞で「iPS 細胞」という言葉を耳にした人、目にした人が多いのではないでしょうか?言葉はよく聞くけど、iPS 細胞って何?、私たちの生活の中で何か役に立つの?、と思っている方も多いのではないでしょうか。では、iPS 細胞とは何かについて、少し説明しましょう。
iPS 細胞(人工多能性幹細胞、induced Pluripotent Stem cells)とは、2006 年に京都大学の山中伸弥教授らのグループによって成体のマウス皮膚から世界で初めて作られたもので、レトロウイルスを用いて体細胞へ数種類の遺伝子 (Oct3/4, c-Myc, Sox2, Klf4) を導入することにより、ES 細胞(胚性多能性幹細胞、Embryonic Stem cells)のように非常に多くの細胞に分化できる分化万能性と、分裂増殖を経てもそれを維持できる自己複製能を持たせた細胞である。この開発をきっかけに、世界各国の研究者が iPS 細胞の作製を開始し、翌年の 2007 年には、ヒト iPS 細胞が作製された。その後、ES 細胞を用いた再生医療から iPS 細胞を用いた再生医療へシフトしている。その理由として、ES 細胞には解決しなくてはいけない問題が存在するため、実際に医療で使用するのは難しいと考えられているためである。
ES細胞は、他人(非自己)の受精卵(初期胚)より作られるため、自己の免疫機構が働き、拒絶反応が起こってしまう。そのため、仮に ES 細胞を移植して健康を取り戻したとしても、免疫抑制剤を服用し続けなくてはいけなく、感染症に注意が必要になる。
iPS細胞は、移植を受ける患者自身の皮膚細胞から作りだすことが可能であるため、拒絶反応の無い移植用組織や臓器の作製が可能になると期待されている。また、胚盤胞を滅失することに対する倫理的問題の抜本的解決に繋がることから、再生医療の実現に向けて、世界中の注目が集まっている。
iPS 細胞を再生医療(治療)に使う試みが世界中で行われている。2008年には神経変性疾患(筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、ハンチントン病、筋ジストロフィーなど)や代謝性疾患(若年性糖尿病など)での成功例が報告され、2009年には血液疾患(地中海貧血、ファンコニー貧血など)や神経変性疾患(脊髄性筋萎縮症や家族性自律神経失調症など)での成功例が次々と報告されている。これらの疾患は、これまでにも有効な治療方法(根本治療)が確立されておらず、その多くが難病に指定されているため、iPS 細胞による再生医療への期待が高まっている。さらに、iPS 細胞は再生医療への応用だけでなく、検査、薬の効き目や副作用の確認、疾患の原因究明(研究)など、その可能性は広範囲に広がっている。
iPS 細胞のメリットばかり述べてきたが、iPS 細胞にも解決しなくてはいけない課題がある。その課題は「iPS 細胞のがん化(腫瘍化)」である。はじめにも述べたが、iPS 細胞はレトロウイルスを用いて、体細胞へ数種類の遺伝子 (Oct3/4, c-Myc, Sox2, Klf4) を導入して作られている。その一つの原因として、これらの遺伝子を体細胞の染色体ゲノム DNA に導入するための「運び屋(ベクター)」として利用しているレトロウイルスである。レトロウイルスベクターは、目的遺伝子を体細胞の染色体ゲノム DNA に導入するが、その際、組み込まれる位置はランダムに決まる。そのため、細胞にとって重要な遺伝子がベクターの組み込みによって破壊され、細胞のがん化を引き起こす可能性が考えられている。現在、この問題を克服すべく、レトロウイルスベクターに変わる方法を世界中の研究者たちが開発に取り組んでいる。
このコラムでは、現時点での、再生医療における iPS 細胞のメリットおよびデメリットを簡単に紹介させていただいた。iPS 細胞の開発は、これまで難治性疾患(治療薬や治療法がない難病)の根本治療にも繋がり、その可能性が期待されることから、今後の研究の進捗が楽しみである。
再生医学とは、胎児期にしか形成されない人体の組織が欠損した場合にその機能を回復させる医学分野である。再生医学を行う手法として、クローン作製、臓器培養、多能性幹細胞(ES細胞、iPS 細胞)の利用、自己組織誘導の研究などがある。将来的には遺伝子操作をした豚などの体内で人間の臓器を養殖するという手法も考えられている。自己組織誘導については、細胞と、分化あるいは誘導因子(シグナル分子)と、足場の 3 つを巧みに組み合わせることによって、組織再生が可能になるとみられており、従来の材料による機能の回復(工学技術にもとづく人工臓器)には困難が多く限界があること、臓器移植医療が移植適合性などの困難を抱えていることから、再生医学には大きな期待が寄せられている。