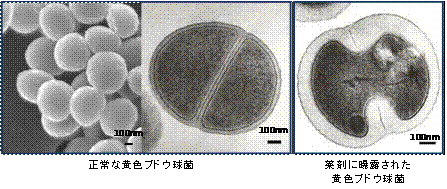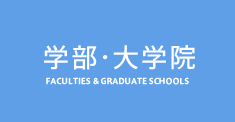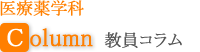小さな生き物たちの大きな力
衛生・微生物学研究室 川井 眞好 講師
微生物、いわゆる「バイ菌」たちは感染症・食中毒などヒトに病気を引き起こす「怖いもの」というイメージがあります。実際、インフルエンザや多剤耐性菌など様々な感染症に関する記事、今のような冬の季節にはノロウイルスなどの食中毒に関する記事などが、新聞紙上を賑わしています。10μmあるいはそれ以下の微生物が、力を結集して1m以上の我々を病気にするのですから確かに「怖いもの」です。このように、微生物たちは小さいにも関わらず、とても大きな力を秘めています。今回のコラムでは、私の感じている微生物のもつ大きな力と魅力についてご紹介します。
微生物の大きな力は、我々の生活をとても豊かにしています。例えば、パン、チーズ、漬物、ヨーグルト、納豆、味噌、しょうゆ、お酒、ワインなどは微生物によって作られています。また、抗生物質などの医薬品や農薬の一部も微生物が作っています。猛毒なボツリヌス菌毒素もその筋肉弛緩作用を利用して治療やシワを取る美容整形に用いることもあります。一方、環境に目を向けると、メタンガス、水素ガス、さらには石油を作り出す微生物もいます。つまり、微生物がエネルギーを作り出すのです。廃水浄化のように私達が汚した環境を浄化してくれる微生物もいます。さらに、現在の科学技術で欠かすことができない遺伝子増幅は、熱に強い微生物がもつ酵素によって進歩しました。微生物は現在の遺伝子工学の発展にも大きく貢献しています。このように、私達は微生物が作り出すものを利用して豊かに過ごしているのです。
微生物は、地下数kmから地上数十kmまで生存していることが確認されており、地表でも、水道水などの水、空気、土など、あらゆる環境で生存しています。微生物が住む環境は、栄養不十分、高温、低温、乾燥など微生物にとって必ずしも住みやすいものではありません。このような自然界の厳しい環境中で生き残るために、微生物は様々な戦略を立てています。地下の高温環境では熱に強い機能をもち、上空の紫外線の強いところでは紫外線にある程度強い微生物が生きています。栄養分の少ない自然環境中で生き残るために、特殊なタンパク合成システムを誘導させて飢餓状態に耐えている微生物もいます。このときは細胞のサイズも機能も抑えて、自己のエネルギー消費を最小限にしています。
さらに、体内および自然環境においては、人間が使った多くの抗菌剤や消毒薬などの抗菌性物質が存在し、微生物はそれらの化学物質に曝露され続けています。実際、廃水、河川水、底泥、土壌などの自然環境中には様々な抗菌剤が数ng/Lや数百ng/gの濃度で残存すると言われています。最近、このような低濃度で致死量以下の抗菌剤に微生物が曝露されることにより、微生物の活性酸素を産生する機能が刺激され、発生した活性酸素によってDNA損傷を引き起こし突然変異発生率が増大することがわかってきました。つまり、抗菌剤の曝露による突然変異が厳しい環境に適応した微生物(耐性菌)に変えることを促進
します。また、微生物は栄養状態が悪いとストレスに対応するシステムが動き、抗菌性物質に抵抗性を示すようになることも報告されています。