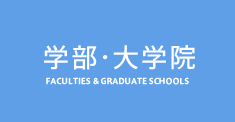色素が織りなす光と生物のコミュニケーション
有機化学研究室 山中 理央 講師
生物と色素:
生物は、光合成生物かそうでないかにかかわらず、光に対して何らかの応答をしています。多くの生物にとって、生きるために光は必要です。生物の光との関わり方は様々ありますが、私は、光合成生物を用いた研究を行っていることもあり、生物が光をどう感じるのかに特に興味があります。
光合成生物において、光を利用するための機能を有しているのは色素です。色素分子により吸収された光エネルギーは光合成に利用され、生物にとって有用な物質を合成します。しかし、いくら光が必要だからといっても、過剰に光をあて過ぎると、光合成が盛んになり過ぎて有害な過酸化物が過剰になり逆に弱ってしまいます。過度な光は害になるのです。同じものが善にも悪にもなるということでしょうか。うまく生きるためには、バランス感覚が必要になるのです。このため、光合成生物は多重の制御機能を備えています。光環境に対する応答の仕方はきわめて多様ですが、その一つとして色素の組成と含量の調節等があります。色素は、320-760 nmの波長範囲の光量子を選択的に吸収し、電気的に励起される分子です。色素は、主に、①光合成を行うためのエネルギーの吸収と伝達する機能と②都合の悪い光の吸収する機能を有していますが、さらに③植物−動物間の視覚的コミュニケーションを助けるはたらきをすることがあります。代表的な色素として、緑色の葉緑素(クロロフィル)、赤色のアントシアニン、黄色のカロテノイド等が知られています。
ラン藻色素の光環境への対応:
私が研究に用いている生物は、ラン藻という藻類の一種です。ラン藻も光合成をしてエネルギー源を獲得しますので、生きるためには光が不可欠です。
ラン藻は、光を吸収するために2種類の色素を持つことで光を適切に利用しています。ラン藻は漢字で書くと藍藻と書き、これは体が藍色であるに由来するのです。通常、光合成生物の代表格である植物は緑色と思うことでしょう。植物の色は色素の色に由来しています。つまり、普通の植物は緑色の色素(クロロフィル)を持つため緑色をしているのです。ラン藻の場合は、もちろん緑色の色素(クロロフィル)も持っていますが、それ以外に藍色の色素(フィコシアニン)も持っているのです。この2種類の色素は吸収する光の波長が異なり、ラン藻は、体内の2種の色素の割合を変化させて、光環境にうまく対応しているのです。

<ラン藻>
リンゴ色素の光環境への対応:
ラン藻以外の生物でも色を変化させるものは数多くあるでしょうが、生物の色の変化に関して面白い話を本で読んだことがあります。『リンゴの色は緑なのか赤なのか』という議論です。リンゴと言えば、日本やドイツでは赤であり、フランスでは緑となっており、ロシアや英語圏では、「赤」派と「緑」派に分かれるということです。なぜ、同じリンゴでも色の認識が異なるのでしょうか。品種の違いというのもあるでしょうが、色素の面からも面白い解釈ができます。

<緑(王林)と赤(ふじ)のリンゴ>
リンゴには大きく分けて3種類の色素があります。緑色の素であるクロロフィル、黄色の素であるキサントフィル、赤色の素であるアントシアニン(ポリフェノール)です。
赤いリンゴにはアントシアニンが多く含まれており、緑のリンゴではアントシアニンは含まれず、地色の緑のクロロフィルが見えていることになります。クロロフィルは、光を集めて光合成に使うための色素ですが、アントシアニン色素には、吸収した光を光合成に使えるという機能はありません。つまり、赤いリンゴができるのは光合成を過剰に行わせないための防御策であるとも言えるのです。アントシアニンは紫外領域の光をよく吸収するとも言われています。リンゴは、様々な色素を作り分けることで、光と良好な関係を保っており、同じリンゴが赤にも緑にもなり得るわけです。このように、生物にとって体色の変化とは、光環境に対応するための手段と言えるわけですが、一方では、それを見る動物とのコミュニケーションに影響を与えるとも考えられます。つまり、リンゴの色は、人間がリンゴを認識するときに重要な役割をもっているのです。
色と文化(言語):
生物にとっては、体色もコミュニケーションの手段の一つです。コミュニケーションの手段と言えば、人間の場合、言葉であり、色の認識が言語や文化に影響されていることが分かっています。例えば、果実の色素はコミュニケーションに必要なものであると考えられます。つまり、人間は、色によってある果実を認識したり、美味しさや状態等を判断していると思われます。
日本人は、赤いリンゴを好むようです。実際に、日本では、アントシアニン色素によるリンゴの着色が、リンゴの商品価値を大きく左右するそうです。そこで、農家ではアントシアニンの合成を促進して、赤いリンゴを生産する努力をしています。アントシアニン合成は光環境に大きく影響を受けることが知られています。ちなみに、最近では、地球温暖化により着色しにくくなっている可能性もあるかもしれません。アントシアニンが合成されるためには比較的低温(10-20度)が良いとされているからです。日本人が赤いリンゴを好むのは、日本では、リンゴと言えば赤いとされているからだと思われます。日本で初めてリンゴの記録があるのは鎌倉時代中頃で、平安時代か鎌倉時代に中国から日本に移入されたと考えられています。明治になりたくさんの西洋リンゴが日本に入って来ましたが、それらと区別するために和林檎と呼ばれています。この和林檎は見事な赤い色であったようです。
ヨーロッパでは、どうでしょうか。試しに、昔のヨーロッパでの絵画を調べてみました。1880年に描かれたクロード・モネの「リンゴの入った籠」、1895年のポール・セザンヌの「リンゴとオレンジのある静物」では、赤いリンゴと緑のリンゴが混じっています。フランスでは、リンゴと言えば緑のはずでしたが、印象派画家に言わせると少し違うようです。印象派画家は写実的に描くことにあまり興味はないのか、または、色彩にこだわるモネやセザンヌはリンゴと言えば緑であっても、絵の中に赤色を取り入れたかったのかもしれません。色々な時期に色々な地域の人によって描かれた、リンゴの絵として最も古くから存在するアダムとイブの絵も調べてみましたが、やはり、赤と緑のリンゴが混在していました。つまり、ヨーロッパにも日本にも、品種に関係なく赤いリンゴも緑のリンゴも同じように存在している、リンゴが光に対する色素合成によって赤にも緑にもなり得るということになります。
それでは、このような色の認識の違いはどこからくるのでしょうか。同じものを見ても感じ方が異なるのは、各地域の文化の差によるといえるのではないでしょうか。
フランス語には、「vert(緑) pomme(リンゴ)」という色彩名があります。それに対して、日本語には「リンゴ緑」のような色はありません。また、実は、英語にも「apple-green」という色彩名があるようです。このapple-greenは、1648年以来の色彩名だそうです。ということは、当時の英語圏の人々にとってはリンゴと言えば緑色だったのでしょうか。しかしアメリカでは、近代にウォルト・ディズニーが製作した白雪姫で赤いリンゴを用いたため、多くのアメリカ人にはリンゴは赤であるとの考え方が定着してしまったという説もあります。つまり、英語やロシア語のように、広大な地域で色々な民族基盤を持つ人々によって使われている言語では、リンゴでも文化的背景の違いによって赤か緑の二通りに解釈されているのでしょう。それに対して、比較的狭い範囲で使われている日本語のような言葉を母語とする人は、一色として認識しているのかもしれません。しかし、この独特の文化もグローバル化が進むと消滅するかもしれません。
また、西洋でリンゴを表す言葉は大きく分けると2種類になると言われています。英語の「apple」、ドイツ語の「Apfel」、ロシア語の「яблоко(ヤーブロコ)」はリンゴそのものを意味するab(e)lという印欧祖語から派生したもので、南ヨーロッパのフランス語「pomme」は古代ギリシャ語のpeponから派生した言葉でベリー類以外の果実やウリ類を表すそうです。フランスのリンゴはウリと同じ仲間ということから緑色のイメージができたのかもしれません。また、興味深いことに、フランスを含む比較的温暖な南ヨーロッパのリンゴを表す言葉の語源が緑色のウリに共通しているのは、高温では赤い色素(アントシアニン)が合成されにくいという事実に合っています。
このように、人間によるリンゴの色の認識は、光がもたらす実際の色だけでなく、言語と文化に影響されているようです。
光は生物に色々な方法で影響を与えています。光合成生物は自ら生きるために色素を介して光を利用していますが、その副産物として出来た天然物は人間を初めとする動物等にうまく利用されています。光は生物が生きて行くためのエネルギー源なのです。光合成生物を利用した研究としては、様々な色の光を照射して生物の生理的機能が変化させるのも面白いかもしれません。さらに、それに加えて、光は色素を介して人間を含む動物とのコミュニケーションにも影響を与えていると言えるでしょう。興味深いことに、人間だけが、時に、光と色素の相互作用により実際に見える色以外にも、文化的背景を伴う色の認識を行います。人間は実際に見える色と心の目による色を感じることができるのです。最近では、カラーセラピーのような治療もあります。色彩が織りなす力が人間または生物に与える可能性は計り知れません。
<参考文献>
- 光合成 佐藤公行 朝倉書店
- 植物生理学 Hans Mohr, Peter Schopfer, 網野真一他監訳 Springer(シュプリンガー・フェアラーク東京)
- 日本語と外国語 鈴木孝夫 岩波新書
- 色の名前507 福田邦夫 主婦の友社